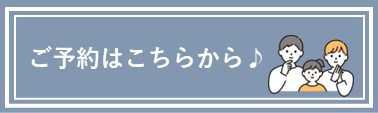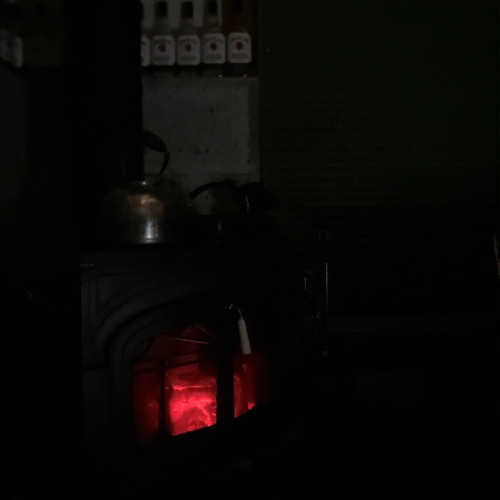コラム
つながりがくれるもの
いつも薪を買いに来てくれるアンティ・マキさん。
「設楽町でマルシェがあるのよ」とチラシをいただきました。
その時、マキさんが小さい頃設楽町に住んでいたこと、設楽町には電車が走っていて当時は栄えていて映画館も二件あったことなどお聞きし、
マキさんのSNSで見かけていつかは行きたいと思っていたマルシェにさらに興味がわきました。
その日は友人のYちゃんと、そのご主人と行く事に。
友人は豊田市から設楽町にお嫁入して、子育ての期間住んでいたことがあるのです。
友人のご主人が生まれ育った場所でもあります。
マルシェは”Kamomilla8周年イベント清崎EXPO2025”といいます。
カモミッラはモザイクアートのお店でイタリア人のエレナさんが移住してお店を始めて8年ということらしいです。
現地ではライブやワークショップ、雑貨や食べ物の販売がありきっと普段は落ち着いている街並みもたくさんの人でにぎわっていました。
中でもエレナさんのご両親が来られていて実現したイタリアバンドというライブは地元の老若男女とマルシェのお客さんが一体となってとても暖かい空気に包まれていました。
私はアンティ・マキさんのすっぱいパン(硬くて焼くと香ばしくてオリーブオイルと塩で食べたらおいしかった)を買い、カレーを食べ、カンナくずイヤリングを買い、マルシェを満喫しました。
帰り道、友人のご主人がここに水車小屋があって、ここに製材所があってなど当時の姿を教えてくれました。
素敵だなと思ったのは、移住されたエレナさんがイベントをされるのを地元の方が暖かく受け入れかつ楽しんでいること。
移住者の方々が少しづつ増えてイベントもにぎやかになってきたのかなと想像していました。
友人のご主人はずっと誰かと話しているし、友人も久しぶりの人に会えたりで私まで嬉しい気持ちになりました。
忙しい毎日、いろいろなつながりの中で自分が生きてこられていることを忘れてしまうときもあります。
でも町の人たちの暖かさに触れ思い出す事ができたそんな一日でした。
アンティ・マキさんお誘いいただきありがとうございました。
二世帯住宅の将来を考える
先回、二世帯住宅についてコラムを書かせていただいたのですが、
その将来の事を考えてみると・・・
完全分離型の二世帯住宅の場合だと一世帯分空いてしまった時に賃貸で貸し出すことも考えられます。
もしくは、お孫さんが成長され、家庭を持たれたときに住むこともできます。
便利な場所で、法令が許せば店舗として貸し出すことも可能です。
ご自身が事業をされることも考えられます。
最初、コストやスペースなどのハードルがクリアできれば建物があるということは考え方によってはリスクではありません。
逆に親が建ててくれた大きすぎる家に完全同居している私としては今の家を将来も住み継いでいってもらえるか少し不安です。
家は建てたときのままお金がかからない、なんてことはありません。
なので、建てる時に、リフォームする時に、少しでも長く使える選択肢を選んでほしい。
そして将来のメンテナンスのお金の出どころは誰なのか、貯金をする、賃貸、、、。
今、二世帯住宅を検討されている方はそんな選択肢もあるという事をお考えいただけたらと思います。
二世帯住宅を考える
先日、家づくり百科というインスタライブで浜松の樹々匠建設の大木さんも言われていましたが、「二世帯住宅はそれぞれの世帯が気を遣わないで済むようにつながり方を考える。」が正解だと思います。
二世帯住宅は親世帯と子世帯がつながっていることで、さまざまな恩恵を受けることができます。
親世帯は、高齢になった時そばにいてもらえる安心感。
子世帯は、子育ての時にそばにいてもらえる安心感。
その他税法上や子世帯は土地を買わなくてよい、親世帯は先祖代々の場所を引き継いでもらえるなど。
ただお互いのプライバシーが守られることが前提にありますよね。
お風呂の時間や順番を気にするのも、食事の時間やメニューを合わせるのも家族の誰かに負担がいってしまいます。
建物としてのつながり方は家族のつながり方にも関わってきます。
その場合、完全分離型の二世帯住宅という選択肢があります。
私はもし可能ならば上下も横もなるべくくっついていないのが理想的だと思っています。
戸建てのメリットは誰かの生活音を気にしなくてよいことだと思うのでその音がおじいちゃんや孫のものであってもなるべく気にならない方がいいと思うのです。
三年ほど前、弊社で働いていたIさんがご主人のご実家に二世帯住宅を建てることになりました。
つながり方の大切さをお話して、お庭を挟んでつながる平屋の親世帯と二階建ての子世帯の構想がまとまりました。
二世帯住宅はそれぞれの世帯のご希望や、土地の形状、高さ関係、駐車スペースなどハードルは通常の戸建て以上にいろいろあります。
でもそれを乗り越えて得られるものは大きいのかなと思っています。
今もご主人やご両親と仲良く暮らすIさんを見て本当によかったなと思っています。
古民家リノベ《はらっぱの家》 庭づくり
先日、お庭工事で古い瓦を敷きこみました。
通常、工事で古い材料を使おうと思うと敬遠されることが多いです。
古材は形も量も不確定。
そして今回はそれをただただ敷き詰めてゆくという工法です。間には砂利や砂が入れられます。
コンクリートで固めてしまった方がもしかして安定していてよいかも知れません。
でも固めない方法が今回の場所には適しているのだと思いました。
建物の周りは常に雨や湿気にさらされています。
新しい建物ならば、少し周囲より高く地盤を設定すればよいですが、今回はリノベーションだったため、
地盤を上げることが難しく、逆に周囲の地盤を保ちながら水の流れを強制的に建物から遠ざけるという手法をとることになりました。
それを古い建物に使用していた瓦でつくることができる。
それは私にとって大変うれしいことです。
今回のお庭の提案をしていただいた、green botanikcal gardens の角谷さんに感謝感謝です。
まだまだお庭造りは続きます。
私も瓦運び、砂運び、できることはしますので、、。
今後ともよろしくお願いいたします。
■■見学会■■
OPEN HOUSE 構造見学会
3月29日㊏~3月30日㊐
10:00~16:00
予約制
参加費:無料
場所:豊田市中金町
※詳細はご予約時にお伝えします
薪ストーブの効能
先日、豊田市の山間部で天候不良による停電が起きました。
私が子供の頃は停電も珍しくなく、家族でろうそくの明かりで夜を過ごすこともありました。
子供のころなので大人がどれだけ大変だったかはわかりません。
停電となると明かり、煮炊き、暖房と困ることはいろいろ。
山間部に住み、停電をした監督から暇なのか情報がラインで随時送られてきました。
やることがない。。。
薪ストーブの明かりだけ。。。
☝実際に送られてきた写真。真っ暗な中、薪の火が見えます。
その時思ったのは、
薪ストーブは停電でも使えるのだな。
ということでした。
お湯を沸かして暖をとって。
そして少しの明かり。
薪ストーブというと一部のユーザーさんが使うものというイメージがあるかも知れませんが
いざという時に役に立つ存在なのですね。
■■ 中古戸建物件情報■■
薪ストーブを愉しめる物件があります♪ご興味のある方は是非!!